コラム
Column都市と社会への接続のためのダンス
「ダンス」とは何か、そして、ダンスが「上手い/下手」ということは一体どういうことか。それをずっと考えています。そもそも、ダンスとは、ダンサーとは、一体何を指すのでしょうか。
私は、まず心が踊り、それが身体の動作にも作用することがダンスだと考えています。そして、その行為をする人が、いかなるトレーニングのバックグラウンドに関わらずダンサーと呼ばれるべきなのではないかと思っています。そこに技術は何も必要ないと信じています。あえて必要な技術を挙げるとしたら、心が動き、その揺らぎや不安定さまでも身体に投影出来る素直で勇敢な態度でしょうか。これらの考えが、私がテクニックやトレーニングのバックグラウンドの有無にこだわらず、むしろそれらを一切持たない「ダンサー」たちと作品を作り始めたきっかけの根底にあります。
2021年9月にスパイラルホールで上演された「Pan」は、出演者8名のうち半数の4名がモデルを職業としています。ダンスのトレーニングの経験はありません。作品のテーマは「都市との接続」「社会においてのコミュニティ」でした。彼ら/彼女らとパフォーマンスのコンセプトやリサーチ結果を共有し、それらから想起される自分の経験について語ってもらいました。出演者一人一人が、今、人生のどの場所に立っているのか。どの方向を向いているのか。表現というものを、どういった理由で必要としているのか。こういった問いかけからそれぞれの座標を作っていき、作品のメッセージを運ぶための装置として一人一人に役割を与えていきました。踊らされているのではなく、自分の声として、身体を動かすことが出来るように。これが、いつも稽古場で皆と立ち返る言葉でした。自分の声ではないと感じるのであれば、話し合って、身体を使って試して、個人の声を一緒に探していく。稽古はその繰り返しです。稽古期間には、参考としてピナ・バウシュの資料をよく読みました。

全体の演出としては、あくまで作品が現実世界と地続きであるように。舞台の向こう側に都市が見えるように。ここではないどこかを求めるマイノリティの人々、それを監視し抑圧する体制側。安全と思われたマイノリティのコミュニティの中でも徐々に亀裂が生じていく。なぜなら社会の構造自体が差別を助長し、弱者を見捨て、破綻しているから。それを、技術に裏付けされていない、どこか不安定な要素を持った現代のリアルな身体を持った若者たちが目の前で体現していく。
この「Pan」は翌月10月にもDance New Air 2020->21のプログラム「ダンスショウケース」内で再演の機会を得ました。この上演ではプログラム自体のキュレーションも私が担当することになり、まさに「ダンスって何だろう?」という疑問をそのままぶつけたようなキャスティングが出来上がりました。子どものような一人遊びや、声やテキストも変幻自在にダンスにする、アオイヤマダと高村月によるアオイツキ。日本の古典を題材とし、それを近松門左衛門的なコラージュの技法で再編し現代へトレースする作曲家・太棹三味線奏者のやまみちやえ×ダンサー安部萌。ピアノを弾くことも、服を纏うことも、舞うことも、全てが唯一無二の美意識で同一線上に存在する清水舞手(SHIMIZU MASH)。それぞれのアーティストによってダンスの定義が目まぐるしく変わるような、見れば見るほどダンスとは、ダンサーとは何か分からなくなるようなラインナップ。キュレーションテーマは「未来への意思表明」。奇しくも翌日の10月31日に衆院選を控えた、30日の上演でした。

このショウケースを上演したこと、そしてこの場で「Pan」を再演出来たことは私にとってとても意義のあることでした。ダンスをどのようにして社会と接続していくのか、どうやって閉塞的な場所からより広い場所へと開放していくのか。そして、自分の声を価値あるものとして大切にすること。これらのことを、様々なバックグラウンドを持ったアーティスト同士や観客が共に考え共有出来る場を得たことは本当に素晴らしい出来事でした。
12月にはKAATの大スタジオで、作曲家・太棹三味線奏者のやまみちやえとの共同制作である「江丹愚馬」(ENIGMA)の上演がありました。元々は2022年1月に映像として企画を進めていた作品ですが、上演の機会をいただけることになり、映像とは全く違う作品として制作をする運びになりました。テーマは「おさめる(govern)」。地下で暴れて大地震を引き起こすと言われていた日本の大鯰(おおなまず)の伝承、そしてその地震を引き起こす張本人でありながら被災地に金をばらまいたり復興を手伝う姿が描かれている鯰絵(なまずえ)を作品の基盤とし、まるで台本の存在する自作自演のような政府の振る舞い、そしてそれを喜んで迎える民衆の姿を作品の核にしました。

上演は義太夫による浄瑠璃と太棹三味線、笛、囃子の生演奏、そして3人のダンサーとフォトグラファーの計10名によって行われました。
そもそも浄瑠璃とは何かを考えた時に、その本質は現代の「実況中継」や「ジャーナリズム」のような役割を持つのではないかと考えました。そのアイディアから出発し、最初はお囃子と一緒に安全な場所にいた義太夫が途中から当事者として舞台上に引っ張り出され、祭り上げられ、出馬し、権力者としての末路を辿っていくという演出プランを立てました。そしてそれを記録し、時には偏った切り取り方をするメディアの象徴として、フォトグラファーには本番の舞台上を自由に移動してもらい、実際に撮影を行なってもらいました。
2021年の「Pan」〜「江丹愚馬」の制作の中で、私はやはり「人の勇気」というものを扱っていきたいのだと再確認することが出来ました。重要なのは上手い、下手という技術への評価ではなく、責任を持って自分の声を上げること。まず心を踊らせること。何かを変えようとするその人の勇気こそが、私が見たいものであり、作品を制作する理由です。そして、その勇気を持って社会と接続していくこと。街と舞台を地続きにさせること。その目的に更に近づくために、私は今後も表現ジャンルや国を飛び越えたボーダーレスな活動を行なっていきます。

**********
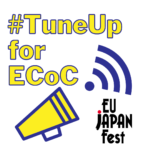
*プッシュ型支援プロジェクト#TuneUpforECoC 支援アーティスト*
https://www.eu-japanfest.org/tuneupforecoc/








